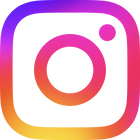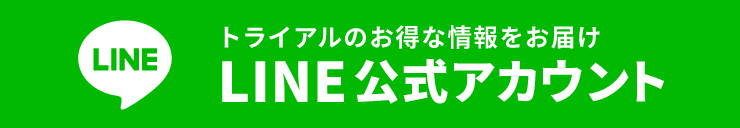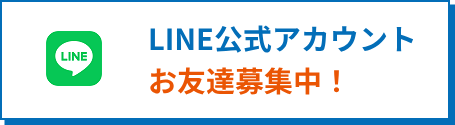ネギの栄養とは?風邪対策にもなる効果的な食べ方を解説
寒い季節になると、ネギを使った料理が食卓に登場する機会も増えてきますよね。
「風邪をひいたらネギ」と昔からいわれるように、ネギには体を元気にしてくれる栄養素がたっぷり含まれています。
今回は、管理栄養士の清水加奈子さんに、ネギに含まれる主な栄養成分や部位や種類による栄養の違い、栄養をムダにしない食べ方のコツについて教えていただきました。
教えてくれたのはこの人!

清水加奈子(しみず かなこ)
フードコーディネーター/管理栄養士
調理師、国際中医薬膳師の資格も持つフードコーディネーター。アイディアレシピやダイエットレシピの提案からフードスタイリングまで幅広くこなし、食関連の企業サイトや雑誌などで活躍中。
公式サイト
トライアルでの販売価格
長ネギ…本体価格198円(税込213円)
※2025年10月メガセンタートライアル八千代店調べ。
※販売価格は時期や産地によって変動します。
ネギの主な栄養成分と期待できる健康効果

ネギには、健康や美容にうれしい栄養成分がたっぷり含まれています。
ここでは、それぞれの栄養成分の働きと体への効果をわかりやすくご紹介します。
硫化アリル(アリシン):血行を促して体をポカポカに
ネギのピリッとした辛みや香りのもとになる硫化アリルは、血行を促進して体を温める働きがあります。
強い抗菌・殺菌作用もあるため、風邪予防にも役立ち、消化を助ける作用もあるので、胃腸の働きを活発にする効果が期待できます。
葉酸:赤血球をつくって貧血予防に
葉酸は、赤血球の材料となるビタミンB群のひとつ。
ビタミンB12といっしょに働き、貧血の予防や妊娠中の健康維持に欠かせません。
ネギでは青い部分に多く含まれていますが、白い部分にもちゃんと含まれているので、丸ごと食べるのがおすすめです。
食物繊維:おなかスッキリ、腸内環境もサポート
食物繊維は、腸の働きを助けて便通を整える働きがあります。さらに、コレステロールの吸収を抑えるなど、生活習慣病の予防にもひと役買ってくれます。
おなかの調子を整えたい方や、健康的な体づくりを目指す方にぴったりです。
ビタミンC:風邪予防と美肌の味方
抗酸化作用のあるビタミンCは、細胞の老化を防ぎ、免疫力を高める働きがあります。
風邪をひきやすい時期や、肌のコンディションを整えたいときにも効果的。
ネギをこまめに取り入れることで、自然とビタミンCをチャージできます。
ビタミンK:骨を丈夫に保つ栄養素
ビタミンKは、骨の形成をサポートし、骨粗しょう症の予防に役立つ栄養素です。
さらに、コラーゲンの生成にも関わっていて、骨だけでなく肌の健康維持にも◎。
年齢を重ねても元気にすごしたい方におすすめです。
ビタミンB6:髪や肌の健康を守る
ビタミンB6は、タンパク質の代謝を助ける栄養素で、健康な皮膚や髪を保つために欠かせません。
美容を意識する方や、成長期の子供にも積極的に取り入れてほしい栄養です。
ビタミンA(β-カロテン):粘膜や目の健康をサポート
ネギの青い部分に多く含まれているβ-カロテンは、体内でビタミンAに変換されて働きます。
目や粘膜の健康を守り、肌のコンディションも整えてくれる抗酸化成分です。
食品成分表には記載がないこともありますが、青い部分にはしっかり含まれていますよ。
ネギの部位や種類によって、栄養に違いはある?

ネギは、白い部分と青い部分で含まれている栄養素が異なります。
さらに、ネギの種類によっても栄養バランスに違いがあるため、目的に合わせた使い分けが大切です。
白い部分には硫化アリル(アリシン)が豊富で、血行促進や免疫力アップが期待できます。
一方で、青い部分にはβ-カロテンや葉酸、ビタミンKなどのビタミン類が多く含まれており、抗酸化作用や美容・骨の健康サポートにも効果的です。
特に長ネギの青い部分は、食品成分表では廃棄部位として扱われることもありますが、実は栄養の宝庫。
炒め物やスープに取り入れれば、ムダなくおいしく栄養がとれます。

また、長ネギ(根深ネギ)、青ネギ(九条ネギ・にらネギ)、小ネギなど種類によっても栄養成分が異なります。
以下に、主なネギの種類と栄養成分を比較した表をまとめました。
ネギの種類別の栄養成分比較(100gあたり)
| ネギの種類 | エネルギー (kcal) | β-カロテン (μg) | 葉酸 (μg) | ビタミンK (μg) | ビタミンC (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 根深ネギ(葉・生) | 28 | 69 | 64 | 42 | 10 |
| 根深ネギ(葉・油いため) | 83 | 72 | 65 | 47 | 12 |
| 小ネギ(葉・生) | 32 | 2,200 | 100 | 340 | 27 |
| 九条ネギ(葉・生) | 32 | 1,800 | 83 | 270 | 25 |
| わけぎ(生) | 29 | 2,000 | 100 | 220 | 25 |
| にらネギ(葉・生) | 31 | 740 | 94 | 200 | 16 |
この表からもわかるように、小ネギやわけぎなどの緑の部分が多い種類には、β-カロテンやビタミンKがしっかり含まれていて、葉酸もやや多め。栄養をしっかり摂りたい方にはおすすめの種類です。
一方で、白い部分が多い根深ネギは硫化アリル(アリシン)の含有量が多く、風邪予防や体を温めたいときに向いています。
ネギの活用ポイント
- 疲れた体をいたわりたい:根深ネギ(白い部分)
- 美容や栄養バランスを重視したい:小ネギ、わけぎ、九条ネギ
- 彩りや風味をプラスしたい:根深ネギ(青い部分)
部位や種類の違いを知って選べば、ネギの栄養をもっと上手に活かすことができます。
薬味としてだけでなく、炒め物やスープ、揚げ物など、いろんな料理に積極的に取り入れてみてくださいね!

長ネギの保存方法は?冷蔵・冷凍・常温で日持ちさせる方法を解説
栄養を逃さない!ネギの効果的な食べ方
ネギは栄養豊富な食材ですが、調理の仕方によってはその栄養が減ってしまうこともあります。
ここでは、ネギの栄養をムダなくとるための調理のコツや、目的に合わせた食べ方のアイディアをご紹介します。
調理のポイント:生と加熱を使い分けて栄養をしっかりとろう

ネギには、熱に弱い成分と、加熱することで吸収がよくなる成分の両方があります。
硫化アリル(アリシン)やビタミンCは熱に弱く壊れやすいため、生で食べる方が効率的。
一方で、β-カロテンやビタミンKは油といっしょに加熱することで吸収率が高まります。
ネギを調理する際は、生と加熱のバランスを意識してみましょう。
生で取り入れたり、加熱してじっくり調理したりして、食べ方を工夫すれば、栄養を逃さず上手にとることができますよ。
生で食べるメリット:硫化アリル(アリシン)をしっかり活かすなら薬味やサラダで

ネギの栄養の中でも、硫化アリル(アリシン)は風邪予防や血行促進に効果が期待できる成分です。
硫化アリル(アリシン)は刻んだ直後が最も豊富に含まれている状態。
時間が経つと揮発してしまうため、刻んだらすぐに食べるのがポイントです。
また、水にさらすと硫化アリル(アリシン)が流れ出てしまうので、なるべく水にはさらさずに使うのが◎。
ネギだれにしたり、サラダに加えたり、うどんや冷奴の薬味として生のまま取り入れると、硫化アリル(アリシン)のパワーをしっかり活かせます。
油といっしょにとる:β-カロテンの吸収率を高める調理法

青い部分に多く含まれるβ-カロテン、ビタミンKは、油といっしょにとることで吸収率がアップします。
おすすめは、炒め物やかき揚げ、オーブン焼きなど油を使う調理法。
斜め切りで繊維を断ち切ると、火の通りもよく、食べやすくなります。
また、ネギは冷凍保存することで繊維が壊れ、加熱したときにやわらかくなりやすいのも特徴。
解凍せずそのまま加熱調理することで、繊維がくずれやすくなり、短時間でも“くたくた”になります。
青い部分も捨てずに、炒めてしっかり栄養をとりましょう。
毎日食べても大丈夫?ネギの適量と注意点
ネギは栄養豊富で、毎日の食事に取り入れたい野菜ですが、食べすぎには注意が必要です。
特に、辛み成分の硫化アリル(アリシン)は刺激が強いため、とりすぎると胃のムカつきやおなかのゆるみといった不調を感じることがあります。
人によっては、唇の腫れやかゆみなどのアレルギー反応が出る場合もあるため、体質に合わないと感じたときは量を控えるようにしましょう。
1日の摂取量に明確な基準はありませんが、目安としては1回30~50g程度(約1/3本)が適量です。
薬味として使うなら10g前後でも十分。
お味噌汁や炒め物など、1日1~2回に分けて少しずつ取り入れると、体への負担も少なく栄養もバランスよくとれます。
胃腸が弱っているときや、おなかを下しやすい方は、加熱してやわらかくしてから食べるのがおすすめ。体調や食べ方に合わせて、無理のない範囲でネギを楽しんでいきましょう。
ネギの栄養を知った今こそ、トライアルで手軽に取り入れよう

ネギは、日常的に取り入れやすい身近な野菜でありながら、風邪予防や免疫力アップ、美容、疲労回復など、さまざまな健康効果が期待できる栄養素を豊富に含んでいます。
もっとネギを活用したいと感じた方は、ぜひ今日のお買い物で新鮮なネギを手に取ってみてください。
トライアルでは、産地や品質にこだわった新鮮なネギを、いつでも手ごろな価格でご用意しています。
炒めても、生でも、薬味にも主役にもなるネギ。
まずは1本から、おうちの食卓にプラスしてみませんか?

おいしい旬の食材がいつでも安いのはなぜ?トライアルの生鮮食品の秘密