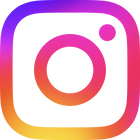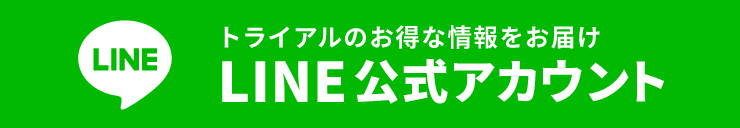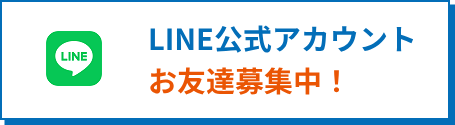レバーの栄養は貧血や疲労に効果的!効率的なとり方も紹介
貧血予防や疲労回復に効果的な食材として、真っ先に名前を挙げる人も多いレバー。
実はレバーには、ほかにも知られざる効能がたくさんあり、とりわけ高い美容効果が期待できます。
独特の臭みやクセも、下処理をすれば気にならなくなりますよ。
今回は、レバーの主な栄養素の働きとその効能、栄養を逃さない食べ方について、管理栄養士の清水加奈子さんに聞きました。
教えてくれたのはこの人!

清水加奈子(しみず かなこ)
フードコーディネーター/管理栄養士
調理師、中医薬膳師の資格も持つフードコーディネーター。アイディアレシピやダイエットレシピの提案からフードスタイリングまで幅広くこなし、食関連の企業サイトや雑誌などで活躍中。
公式サイト
トライアルでの販売価格
豚レバー(200g)…198円(税込)
鶏レバー(100gあたり)…79円(税込)
※2024年10月 メガセンター八千代店調べ。
※販売価格は時期や産地によって変動します。
レバーに含まれる栄養素は?
レバーが体に良いことは知っていても、具体的にどのような栄養素が含まれているかは知らない人が多いかもしれません。
まずは、レバーに含まれる栄養素を紹介します。
タンパク質
タンパク質は、筋肉や髪、皮膚、爪など、体のさまざまな組織のもとになる栄養素です。
筋肉量を増やして体格を良くしたい人や、基礎代謝を高めてやせやすい体をつくりたい人には必須の栄養素だといえるでしょう。
ビタミンA
夜間の視力を維持し、皮膚や粘膜を強くする働きがあるビタミンA。
レバーのように動物性の食品に含まれるビタミンAは、植物性食品から摂取するよりもスムーズに体に吸収される特徴があります。
過剰摂取には注意が必要ですが、効率良くビタミンAを補いたいときにレバーは最適です。
ビタミンB群
レバーには、ビタミンB群のうちビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB12、葉酸が含まれています。
ビタミンB2やナイアシンは、脂質・糖質・タンパク質の代謝や糖質の分解を促すため、新陳代謝を助けて皮膚や爪を強くする効果が期待できるでしょう。
ビタミンB12は、葉酸とともに赤血球のヘモグロビン合成を促進します。
また、レバーはビタミンBの一種であるパントテン酸含量が5.0mg(可食部100gあたり)を超える食品です。
パントテン酸は脂質や糖質の代謝に役立つほか、善玉コレステロールを増やしたり、ホルモンの産生に寄与したりします。
ミネラル(鉄分、亜鉛)
鉄分と亜鉛は、体を構成する骨や細胞の材料になったり、神経や筋肉、ホルモンの働きを調整したりするミネラルのひとつで、どちらも赤血球に含まれるヘモグロビンの合成に関わります。
特に鉄は、成人の体内にある約3~5gのうち70%がヘモグロビンや筋肉の中のミオグロビンに存在し、残りの30%が筋肉や肝臓、骨髄などにストックされています。
鉄分の摂取量が減ると赤血球の数が減り、頭痛や食欲不振、集中力低下などを引き起こす「鉄欠乏性貧血」の原因に。
ミネラルは体内で生成することができないため、食事からしっかり鉄分をとることが大切です。

レバーの種類ごとの栄養素の違い
一般家庭で主に食べられているレバーは、牛、豚、鶏の3種類です。
含まれている栄養素はどれもほぼ同じですが、栄養素の量には違いがあるため、効果・効能にも多少の差があります。
レバーの種類ごとの栄養素比較(100gあたり)

上の表から、レバーは種類を問わずタンパク質が豊富で、ビタミンB群もしっかりとれることがわかります。
特に大きな違いがあるのはビタミンAで数値を比較すると、含有量に1桁の差があります。
少量のレバーでしっかりとビタミンAをとりたいときは豚や鶏レバーが良いでしょう。
鶏レバーはほかの2つに比べてカロリーが低い上に脂質が若干少ないため、ダイエットにも向いています。
ただし、コレステロールは高いため、とり過ぎには注意してください。
一方、レバーに期待される貧血防止効果については、鶏レバー、牛レバーよりも、鉄と亜鉛が多い豚レバーに軍配が上がります。
レバーを食べることで期待できる効果
続いて、栄養豊富なレバーを食べることによって期待できる効果について見ていきましょう。
老けない体をつくる
レバーに含まれるビタミンAは、強力な抗酸化作用を持っています。
抗酸化作用とは、私たちが取り込んだ酸素の一部が変化してできる活性酸素を抑制する働きのこと。
活性酸素が過剰になると体が酸化して老化が進んだり、病気の原因になったりします。
ビタミンAをとることで、病気になりにくい若々しい体を維持することができるでしょう。
ビタミンAには粘膜の新陳代謝を活発化する働きがあり、肌のハリや潤い、弾力を保つのにも役立ちます。
貧血を予防する
レバーは、赤血球のヘモグロビン合成に欠かせない葉酸と「造血のビタミン」ともいわれるビタミンB12、鉄分を多く含みます。
鉄分には、動物性の食品に含まれる「ヘム鉄」と植物性の食品に含まれる「非ヘム鉄」があり、レバーに多く含まれるヘム鉄は、非ヘム鉄に比べて体への吸収が非常に良いのが特徴です。
レバーから適量のヘム鉄、葉酸、ビタミンB12を合わせて補給することで、ヘモグロビンの欠乏を防ぎ、貧血を予防・改善することができます。
外見を若々しく保つ
レバーの豊富な栄養素のうち、ビタミンB2は、タンパク質・脂質・糖質という三大栄養素をエネルギーに変換するのを助けます。
ビタミンB2は、肌の新陳代謝を促進して再生を促すため、皮膚や爪、髪などを良い状態で維持することができるでしょう。
ナイアシンにも、皮膚や粘膜を保護する効果があります。

レバーの栄養を逃さずとる方法
レバーの豊富な栄養素を余さずにとるには、どのような食べ方がいいのでしょうか。
調理の際に合わせる野菜や、効果的な調理の方法などを理解して、効率的に栄養を摂取しましょう。
ビタミンCといっしょにとる
レバーに含まれるヘム鉄は、ビタミンCといっしょにとることで吸収率がアップします。
トマト、パプリカ、ブロッコリーなど、ビタミンCを多く含む野菜と合わせて調理しましょう。
レバーパテの仕上げに柑橘を絞るなども有効です。
油で調理する
ビタミンAは脂溶性のビタミンのため、油に溶けだすことで吸収率がアップします。
ビタミンCが豊富な野菜とレバーを油で炒めて食べると、鉄分とビタミンAの吸収率が上がって一石二鳥です。
レバー料理の定番、レバニラ炒めは効果的にレバーの栄養をとれる料理といえるでしょう。
レバーを食べるときの注意点
栄養価の高いレバーは、普段の食事に積極的に取り入れたい食材ですが、いくつか注意点があるため、食卓に並べる際は次のことを意識することをおすすめします。
しっかりと下処理をする
レバーには独特のくさみがあるため、しっかりとした処理をすることが肝心です。
ご家庭でも簡単にできる下処理方法を過去の記事で紹介していますので、ぜひトライしてみてください。

レバーの下処理の方法とは?簡単にくさみをとっておいしく食べよう
食べすぎに注意する
レバーに含まれるビタミンAは、過剰摂取すると腹痛や悪心、嘔吐、めまいなどを引き起こすことがあります。
妊婦さんなど、貧血予防にレバーを食べるのは良いことですが、牛レバーなら1日30g程度、鶏や豚レバーなら週に1~2回30g程度にとどめましょう。
保存方法に注意する
レバーはほかの肉類に比べて、足が早いのが特徴です。
正しい方法で保存して、鮮度を保つように心掛けましょう。

きちんと下処理した後のレバーは、2週間を目安に冷凍で保存することで鮮度を保ったまま保存できます。
詳しい保存方法も下記の記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

レバーの下処理の方法とは?簡単にくさみをとっておいしく食べよう
栄養の宝庫・レバーを食卓に取り入れよう!

レバーは栄養が豊富な食材で、すこやかな毎日をアシストしてくれます。
貧血ぎみの人はもちろん、毎日をもっとエネルギッシュに過ごしたい人も、レバーの栄養素を有効に活用しましょう。
鮮度とお手頃価格にこだわるトライアルの精肉売り場では、お求めやすい価格で新鮮なレバーを販売しています。
お買い物の際は、レバーにも注目してみてくださいね。

トライアルの肉が安くておいしい理由は?鮮度&安心安全へのこだわり