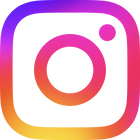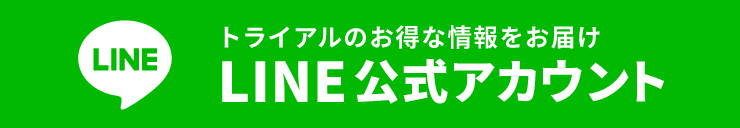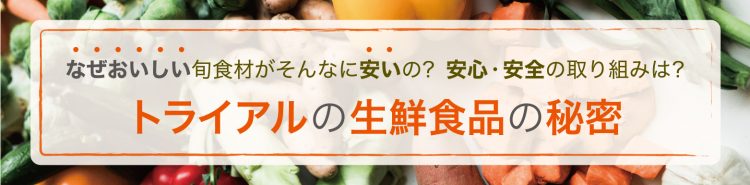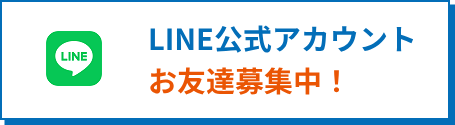お雑煮の具材、お餅の種類は?地域別の違いを調査してみた
皆さんは、毎年どんなお雑煮を食べていますか?地域によって、お餅の形や出汁の種類、入れる具材が異なるのが、お雑煮のおもしろいところですよね。
そこで、トライアルマガジンでは、メールマガジンにご登録いただいているお客様に、お雑煮に関するアンケート調査を実施。全国各地でどのようなお雑煮が食べられているのか、リサーチしてみました!
また、料理家の風間章子さんに教えていただいたお雑煮のレシピもご紹介します。年始は、いつもとひと味違ったお雑煮に、ぜひ挑戦してみてください。
お雑煮を食べる風習はいつから始まった?
一年の無事を祈ってお正月に食べるお雑煮。日本ならではのこの風習は、室町時代の武士の習わしが元になっているといわれています。
当時、武士の宴会では、酒の肴(さかな)として最初にお雑煮が振舞われていました。このことから、お雑煮=宴の始まりを告げる縁起のいい料理とされ、いつしか一般庶民のあいだでも、一年の最初の日である元日にお雑煮を食べるようになったといわれています。
お雑煮は、全国各地で味や具材が異なり、よく知られている物だけでも、その種類は100を超えるほどバラエティ豊か。細かい特徴にまで着目するとさらに種類は増え、「集落の数だけお雑煮の種類がある」ともいわれています。
お餅の形や出汁の種類は?地域別のお雑煮を紹介

今回、トライアルマガジンでは、メールマガジンにご登録いただいているお客様を対象に、どのようなお雑煮を食べているかアンケートを実施(2021年11月)。ここからは、534名の方から寄せられた回答をもとに、全国各地のお雑煮事情をご紹介します!
アンケートの内容
Q1. お住まいの県を教えてください
Q2. お雑煮に入っているお餅の形を教えてください(角餅/丸餅/その他)
Q3. お餅の調理法を教えてください(焼き/茹で/その他)
Q4. お雑煮の汁の味つけを教えてください(醤油/白味噌/赤味噌/その他)
Q5. お雑煮に入れる具材の種類を教えてください
北海道のお雑煮
北海道のお雑煮は、鶏ガラで出汁を取るのが一般的。汁の味つけは醤油ベースで、角型の餅を焼いてから煮込むご家庭が多いようです。
ニンジン、大根、シイタケ、タケノコ、長ネギ、セリ、三つ葉など、野菜をたくさん入れる点も特徴。なるとやかまぼこを入れるといった回答も多く見られました。
東北地方のお雑煮
地域によって、鶏ガラなど肉系の出汁と、ハタハタなど海鮮系の出汁に分かれる東北地方。汁の味つけは醤油ベースで、餅は角型が一般的です。
ニンジン、大根、セリ、三つ葉など野菜のほか、高野豆腐や舞茸などを入れることも。三陸海岸沿いでは、アワビやイクラなど、贅沢な具材を入れるご家庭も多いようです。
関東地方のお雑煮
関東地方のお雑煮は、昆布や鶏ガラで出汁を取り、醤油で味つけをするのが一般的。餅は角型で、焼いてから具材といっしょに煮込みます。
ニンジン、大根、シイタケ、ゴボウのほか、白菜や里芋などの野菜も入れて具たくさんに。珍しいお雑煮文化のある地域も多く、茨城県の一部地域では、すり鉢でこした豆腐を昆布出汁で伸ばし、砂糖を入れて火にかける「白和え雑煮」を食べるそうです。

中部地方のお雑煮
中部地方については、残念ながらアンケートの回答は得られませんでしたが、どのようなお雑煮が食べられているか編集部で調査してみました。
海産物が豊富に獲れる富山県では、エビやブリがドンとのった豪勢なお雑煮が主流のようです。長野県の松本市周辺では、昔から、富山湾で獲れたブリの塩漬けが運ばれていたそう。海のない地域で、魚をハレの日にいただく伝統が今も息づいているといいます。
東海地方のお雑煮
東海地方の中でも、愛知県は八丁味噌のイメージが強いですが、お雑煮は意外にもシンプルなすまし汁仕立て。昆布や鰹節で出汁を取り、醤油で味つけしたすまし汁に、角餅を焼かずに入れて煮込みます。
具材もシンプルで、明治時代から栽培されている伝統野菜である「もち菜」のみというご家庭も多いようです。
関西地方のお雑煮
アンケートの結果、醤油ベースと白味噌ベースの味つけが半々だった関西地方。大阪府ではすまし汁、京都府や奈良県、兵庫県では白味噌が主流のようです。餅は丸型で、焼いてから煮込みます。
ニンジン、大根、シイタケなどの野菜のほか、ユリ根やうす揚げ、焼き豆腐など、具材もバラエティに富んでいます。京都のお雑煮は、京野菜の頭芋(かしらいも)や金時ニンジンを入れるのが定番。雑煮に甘いきなこを添える、奈良の「きなこ雑煮」も有名です。

中国地方のお雑煮
牡蠣や海苔など、海鮮系の具材で出汁を取り、醤油で味つけをすることが多い中国地方。アンケートの結果、餅は丸型が主流で、焼かずに煮込むのがやや優勢でした。
具材は海苔のみといったシンプルな物や、干した鮎など魚介類を入れるといった回答も。鳥取県では、ぜんざいタイプの「小豆雑煮」も古くから親しまれているようです。
四国地方のお雑煮
四国地方についても、残念ながらアンケートの回答は得られませんでした。
編集部で調査してみたところ、四国地方で有名なのは、なんといっても香川県の「あん餅雑煮」でしょう。白味噌ベースの汁に、あん餅を入れたお雑煮は、甘さとしょっぱさが交互に味わえてやみつきになる一品です。
九州地方のお雑煮
地域の特徴が出汁に現れる九州地方のお雑煮。例えば、福岡県では焼きアゴやスルメ、鹿児島県では焼きエビ、宮崎県ではシイタケで出汁を取ります。味つけは醤油ベースが主流で、アンケートの結果、餅は丸型が8割を占めました。
トライアルの本社がある福岡県では、ブリとカツオ菜を入れた「ブリ雑煮」が有名。次のブロックで、作り方を詳しくご紹介します!
年始は例年と違う雑煮に挑戦!2種類の雑煮の作り方を紹介
ここからは、トライアルの本社がある福岡県の「ブリ雑煮」と、白味噌ベースの代表ともいえる京都府のお雑煮の作り方を、料理家の風間さんに教えていただきます。
出世魚で縁かつぎ!福岡県の「ブリ雑煮」

材料(2人分)
アゴ出汁…300ml
シイタケの戻し汁…100ml
ブリ…2切れ
里芋…2個
ニンジン…40g
大根…40~50g
カツオ菜(カキ菜でも可)…2~3枚
干しシイタケ…2枚
かまぼこ…2切れ
丸餅…2個
薄口醤油…小さじ1
塩…小さじ2分の1
酒…大さじ2分の1
[A]
昆布出汁…400ml
みりん…小さじ1
醤油…小さじ1
作り方
1. 干しシイタケ2枚は100mlの水に5時間以上つけて戻す。できればひと晩置くと、ふっくらと戻って食感が良い。
2. 里芋は半分、ニンジンは輪切り、大根はいちょう切りにする。戻したシイタケは軸を取る。

3. カツオ菜は別鍋で色良く塩茹でする(塩は分量外)。
4. ブリに振り塩をし、ザルなどに並べて熱湯をかけて表裏ともに湯引きする(塩は分量外)。

5. 「2」と丸餅を[A]にいれ、やわらかくなるまで下茹でする。茹で上がったらお椀に盛る。
6. アゴ出汁300ml、「1」のシイタケの戻し汁100ml、酒、醤油、塩を鍋に入れて火にかける。
7. 丸餅と野菜の入ったお椀にブリを盛り、出汁をかける。最後にカツオ菜を飾って完成!
ブリのくさみを取る工程を忘れずに
ブリを使うとき、気になるのが魚独特のくさみですよね。お雑煮をおいしくいただくには、くさみを取るひと手間が大切。
鍋にザルを引っ掛けてブリを並べたら、塩を振って30分ほどおき、余分な水分を抜きましょう。さらに「4」の工程で湯引きをし、血合いやぬめりを取り除くと、くさみが取れてふっくらおいしく仕上がります。
上品でまろやかな京都府の「白味噌雑煮」

京都のお雑煮は、甘い白味噌ベース。「家族円満・物事を丸く収める」といった意味を込めて丸餅を使用し、具材もすべて丸く切ります。頭芋や金時ニンジンなど京野菜が手に入らない場合は、里芋や普通のニンジンで代用してもいいでしょう。
材料(2人分)
昆布出汁…300ml
白味噌…100g
頭芋(里芋でも可)…2個
金時ニンジン(普通のニンジンでも可)…40~50g
大根…40~50g
三つ葉…少々
ユズの皮…少々
糸カツオ…少々
丸餅…2個
酒…適量
[A]
昆布出汁…500ml
みりん…小さじ1
醤油…小さじ1
作り方
1. 里芋は皮をむいて半分に切り、金時ニンジンは輪切り、大根はいちょう切りにする。
2. 「1」と丸餅を[A]に入れて火をつけ、やわらかくなるまで下茹でする。茹で上がったらお椀に盛る。


3. 鍋に昆布出汁300mlを入れて火にかけ、沸騰したら火を止めて白味噌を溶く。

4. 野菜を盛ったお椀に「3」を注ぐ。三つ葉、ユズの皮、糸カツオを飾れば完成!
味噌は少しずつ溶き入れるのがコツ
ほかの味噌に比べて甘みがあり、塩味が少ない白味噌。普段、米味噌や麦味噌を使っていると、味の加減がわかりにくいかもしれません。
最初はいつも使っている味噌の分量より少なめの量をお玉に取り、菜箸でほぐしながら2~3回に分けて溶き入れましょう。「もう少し入れようかな?」と思ったタイミングで一度味を見て調整してください。
お雑煮やおせちなど、正月料理の買い物はトライアルで!
全国各地のお雑煮事情と、2種類のお雑煮のレシピをご紹介しました。毎年食べているお雑煮以外に、来年のおお正月にはぜひもう1種類、お雑煮づくりに調整してみてください。
トライアルの生鮮コーナーでは、お雑煮やおせちなど、お正月料理用の食材を手頃な価格で取り揃えています。24時間営業なので、何か買い忘れがあっても安心!ご家族でトライアルを訪れ、年末年始に食べたい物を相談しながら、店内を回ってみてはいかがでしょうか。

監修者プロフィール
風間 章子
料理家/調理師
イタリアンレストランで6年間修行した後、カフェを立ち上げ、雑誌やウェブなど、さまざまなメディアにて料理監修で活躍。これまで、4店舗のカフェの料理メニューの立ち上げを行う。料理の技術向上はもちろん、料理の楽しさを伝えることを目的とし、料理の撮影や料理教室を開催するキッチンスタジオ「人形町キッチン」を運営。わかりやすい説明と気さくな人柄で、好評を得ている。 料理家 風間章子 | FORM☆AGGIO