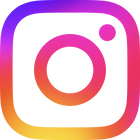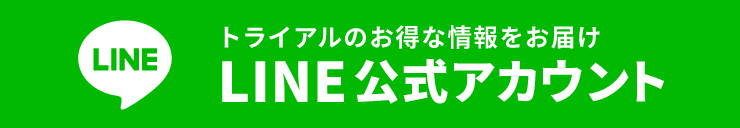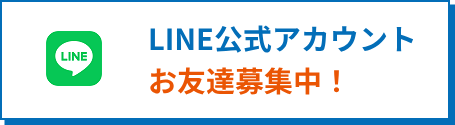長芋は栄養たっぷりでヘルシー。栄養を逃さない食べ方や効能を紹介
古くから滋養強壮の効果があるといわれ、漢方薬の原料になる生薬としても重宝されてきた長芋。
ジャガイモやサツマイモなどと違って生で食べられ、体に良い栄養素を効率的に摂取できるのもうれしいポイントです。
今回は、年間を通じて安定的に手に入り、調理法も多様な長芋の栄養を逃さない食べ方や効能について、管理栄養士の清水加奈子さんに詳しく教えていただきました。
教えてくれたのはこの人!

清水加奈子(しみず かなこ)
フードコーディネーター/管理栄養士
調理師、中医薬膳師の資格も持つフードコーディネーター。アイディアレシピやダイエットレシピの提案からフードスタイリングまで幅広くこなし、食関連の企業サイトや雑誌などで活躍中。
公式サイト
トライアルでの販売価格
長芋(100g)…79円(税込)
※2024年11月 メガセンター八千代店調べ。
※販売価格は時期や産地によって変動します。
長芋に含まれる主な栄養素は?

活力源になる栄養素がたっぷり含まれている長芋は、その栄養価の高さから「山のウナギ」と呼ばれることも。
ここからは、長芋に含まれる主な栄養素を見ていきましょう。
ミネラル
長芋には、カリウムやマグネシウムなどのミネラルが豊富です。
カリウムは、体内の余分なナトリウムや水分を排出する作用があります。
一方で、カリウムが不足すると脱力感や食欲不振、精神的な不安定さなどにつながることも。
マグネシウムは、骨や歯を丈夫にするだけでなく、血圧を安定させたり、筋肉の動きを助けたりする働きがあります。
体内のマグネシウムの多くは骨や歯に含まれ、残りは筋肉や脳、神経に存在して血管を広げる働きをしています。
そのため、脳卒中や心疾患といった循環器系の疾患の予防にも効果が期待できます。
ビタミンB群
長芋はビタミンB群が豊富で、ビタミンB1、B6、パントテン酸を多く含みます。
ビタミンB1は、摂取した糖質をエネルギーに変え、脳や神経の働きを正常に保ちます。
そのため、ビタミンB1が不足すると、集中力の低下や精神的不安、手足のしびれといった症状を引き起こすことも。
ビタミンB6は、筋肉や髪、皮膚、爪などのもととなるたんぱく質の代謝に関わります。
若々しさや健康的な体を保つため、たんぱく質を意識的に摂取している人は、ビタミンB6も併せてとると効果的でしょう。
パントテン酸はビタミンB群の一種で、3大栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物の代謝を促し、エネルギーを産生します。
心臓や血管をはじめとした体の機能の働きを助ける副腎皮質ホルモンの合成にも関わるほか、脂質の代謝を促進するHDLコレステロールを増やす働きがあります。
食物繊維
多くのイモ類に共通しますが、長芋も食物繊維が豊富です。
腸内環境を整えて便通を改善することで知られる食物繊維には、糖の吸収速度を抑える働きもあります。
糖がゆっくりと吸収されることで食後の血糖値の上昇がゆるやかになり、太りにくい体づくりにつながります。
ジアスターゼ(旧名:アミラーゼ、消化酵素)
ジアスターゼは、でんぷんの分解と消化促進に関わる栄養素です。
分解されたでんぷんは糖に変わり、血液中に取り込まれて全身のエネルギー源として利用されます。
長芋には、体の正常な状態に維持し、エネルギッシュに活動するために欠かせない栄養素が豊富に含まれています。
なお、長芋のねばねばの主成分は糖質ですが、吸収が遅く血糖値の上昇を抑える多糖類なので、肥満になるリスクが少ないでしょう。
長芋を食べることで期待できる効果とは?

続いては、長芋を食べることで期待できる効果をご紹介します。
長芋の栄養素は、体づくりにも、美容にも欠かせないものばかりです。
継続的に摂取して、良い体の状態を維持しましょう。
適正体重を保つ
長芋に含まれる食物繊維は、腸内環境に働きかけて便秘を改善します。
また、糖質をエネルギーに変えるビタミンB1、でんぷんを分解するジアスターゼの働きと組み合わさることで、太りすぎを防ぎ、適正体重を維持するのに役立つでしょう。
むくみを防ぐ
余分な塩分と水分を排出するカリウムの働きで、だるさや冷え、顔などの腫れぼったさの原因になるむくみを予防できます。
手足や顔をすっきりさせたい人、疲労感を解消したい人は、積極的に長芋をとることをおすすめします。
美肌を保つ
ビタミンB6が代謝を助けることで、肌のターンオーバーが活性化されます。
その結果、肌荒れやくすみの改善が期待できます。
また、ターンオーバーが正常化することで、メラニンの排出が促されるため、しみを薄くする効果も期待できるでしょう。
骨粗鬆症を予防する
骨の形成や骨量の維持、骨密度の増加に有用なマグネシウムの働きにより、骨粗鬆症を予防できます。
特に、女性ホルモンの一種であるエストロゲンが減ることで、骨粗鬆症を発症しやすくなる更年期世代の女性は、長芋などから意識的にマグネシウムをとることが望ましいです。
長芋とほかのイモ類との栄養素の違い
長芋を含め、ヤマノイモ科に属するイモ類は「山芋」と総称されます。
山芋には、長芋をはじめ、大和芋(いちょう芋)、自然薯があります。
長芋と大和芋、自然薯はどれも同じ栄養素を含んでいます。
ただし、水分量には違いがあり、3種類の中では長芋に含まれる水分量が最も多め。
その分栄養素の量は少なくなりますが、淡泊で粘りがそれほど強くないため、さまざまな料理の味付けや調理法にフィットしやすく、使い勝手に優れています。
■長芋とほかのイモの栄養比較(100gあたり)

長芋を含む山芋と、ほかのイモ類との最大の違いは、「生で食べられるかどうか」です。
サツマイモ、ジャガイモ、里芋といったイモ類は、基本的に加熱しなければ食べられません。
一方、長芋をはじめ、ヤマノイモ科のイモ類は生で食べられるため、茹でることによって流れ出てしまう水溶性のビタミンのパントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB6やカリウム、加熱で壊れる消化酵素も余さずとることができます。
長芋の栄養を逃さないおすすめの食べ方

長芋の特性を理解して食べ方を工夫すると、豊富な栄養素をしっかりととることができます。
ここからは、長芋の栄養素を逃さない食べ方をご紹介します。
生で食べる
前述のとおり、長芋は生で食べられるイモ類です。
茹で調理などの加熱で損失するビタミンB群やミネラル、加熱で壊れてしまう消化酵素をしっかり摂取したいときは、すりおろしたり、短冊切りにしてサラダに加えたりして、生のまま食べましょう。
長芋を生で食べるときに気になるのが、皮とひげですよね。
実は、長芋の皮は見た目の印象よりも薄く、クセがないので、皮つきでも問題なく食べられます。
ひげも、ガスコンロなどを使い炙ると口に残らず、香ばしさが増すのでおすすめです。
余ったら冷凍する
長芋は、すりおろして冷凍しても栄養価が変わりません。
特にミネラル、糖質、食物繊維、ビタミンB群の量は冷凍前後でほぼ変わらないため、たくさん買ったときはすりおろして小分けし、冷凍しておくと「栄養素のちょい足し」ができて便利です。
おすすめは、1口大の大きさに小分けしてラップで包み、ジッパー付き保存袋にいれて冷凍する方法。
流水や冷蔵庫ですぐに解凍できるので、温かいごはんに乗せたり、麺類のつゆにいれたりして楽しみましょう。
温かいスープなどに使う場合は、凍ったまま入れてもかまいません。
栄養価の高い長芋で、寒い冬を乗り切ろう

長芋には、エネルギーを維持して健康的に過ごすために必要な栄養素がたっぷり含まれています。
ほかのイモ類と違って生のまま食べられるため、もう1品ほしいときにも活躍してくれますよ。
冷凍しても栄養素は変わらないので、安価なときにまとめ買いをして冷凍しておくのがおすすめです。
トライアルでは、旬の時期はもちろん、年間を通してお手頃な価格で長芋をご提供しています。
トライアルで長芋を購入して、体調を崩しやすい冬を乗り切りましょう!

野菜・果物など毎日食べたいトライアルの青果、鮮度と味へのこだわり