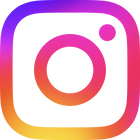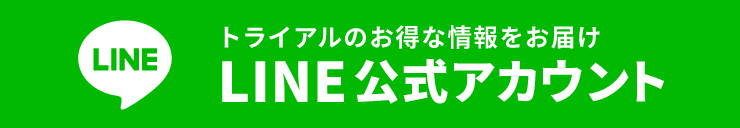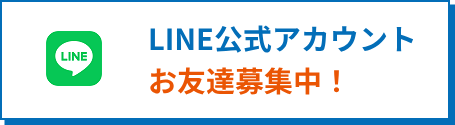【梅シロップの作り方】下準備や保存方法、よくある疑問を解消
梅シロップは、梅と砂糖で手軽に作れる、季節の手しごとです。
爽やかな風味と甘酸っぱさが魅力で、夏場には炭酸水や水で割って自家製ドリンクとして楽しむ方も多くいます。
初めて作るときは、「うまくできるか不安」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、きちんと手順を守れば失敗せずにおいしく作ることができます。
今回は、梅シロップ作りの下準備から完成までの手順を料理家の風間章子さんに教えていただきました。
保存のコツや活用方法のほか、梅シロップ作りでよくある質問にも答えていますので、ぜひ参考にしてください。
教えてくれたのはこの人!

風間章子(かざま あきこ)
料理家/調理師
イタリアンレストランで6年間修業した後、カフェを立ち上げ、雑誌やウェブなど、さまざまなメディアにて料理監修で活躍。これまで、4店舗のカフェの料理メニューの立ち上げを行う。料理の技術向上はもちろん、料理の楽しさを伝えることを目的とし、料理の撮影や料理教室を開催するキッチンスタジオ「人形町キッチン」を運営。わかりやすい説明と気さくな人柄で、好評を得ている。
X(旧Twitter):@ACCO_kzm
目次
トライアルでの販売価格
青梅(2L)…本体価格798円(税込877円)
青梅(3L)…本体価格980円(税込1,056円)
氷砂糖…本体価格398円(税込429円)
※2025年6月 メガセンター八千代店調べ。
※販売価格は時期や産地によって変動します。
【下準備から完成まで】梅シロップの作り方

ここでは、梅シロップを作るための基本的な手順をご紹介します。
材料はシンプルですが、丁寧な下準備が梅シロップ作り成功のポイントです。
材料(作りやすい分量)
青梅…1kg
氷砂糖…1kg
(梅と氷砂糖は同量にする)
用意するもの
保存瓶(3L)
竹串または爪楊枝
アルコールスプレー
ビニール手袋

手順
1. 竹串または爪楊枝で青梅のヘタを取り除き、水で優しく洗う。

2. キッチンペーパーを使って一粒ずつ丁寧に水気を拭き取る。ヘタのくぼみ部分にも水が残りやすいため、念入りに行う。

青梅のヘタのくぼみに水分が残っていると、カビが発生する原因になるため、しっかり拭き取りましょう。
3. 保存瓶の内側にアルコールスプレーを吹きかけ、殺菌・消毒をする。耐熱製の瓶の場合は、常温の水を張った鍋に入れ、火にかけて煮沸消毒してもOK。

瓶の内側に雑菌が残っていると、発酵やカビの原因になります。
また、煮沸消毒の場合、保存瓶が割れるおそれもあるため、熱湯を直接注ぐのはNGです。
商品によっては、消毒方法の記載があるため、取り扱いを事前に確認しましょう。
4. ビニール手袋をして、「青梅→氷砂糖→青梅→氷砂糖」の順で、交互に青梅と氷砂糖を保存瓶に入れていく。




5. 青梅を入れ終えたら、最後に氷砂糖を多めに入れる。

一番上に氷砂糖を多めにのせると、青梅が空気にふれにくくなるため、カビの予防につながります。
6. 青梅と氷砂糖を瓶に詰めたら、1日に2~3回、瓶を傾けて優しく転がす。

保存瓶を転がす作業は、できるだけこまめに行うのが◎。
定期的に転がすことで、青梅のエキスと溶けた氷砂糖が残体に馴染み、より均等にエキスが抽出されます。
7.2~3 週間経ち、実から十分にエキスが出たら、青梅を取り出す。

あまり長く漬け込むと、青梅の苦味やえぐみがシロップに移ってしまうこともあるので、注意しましょう。
8. エキスをザルで漉して、鍋に入れて火にかけ、沸騰直前に弱火にする。そのまま15分程火にかけ、冷ます。

梅酒の基本的な作り方――初心者でも失敗しにくい梅仕事
梅シロップの保存
完成した梅シロップは、保存瓶のままだと場所を取るため、小ぶりな密閉瓶に移し替えておくと使いやすくなります。
保存期間は、冷蔵庫に入れて3~4ヵ月、煮沸してから保存する場合は、半年が目安です。
煮沸すると、殺菌に加え、発酵してしまった時の発酵臭やアルコール臭を取り除くことができます。
常温保存も可能ですが、発酵やカビのリスクが高まるため、なるべく早めに飲み切るようにしてくださいね。
梅シロップはどう使う?

完成した梅シロップは、さまざまな使い方で楽しめます。
炭酸水や冷水で割ってドリンクとして楽しむ方法が一般的です。
爽やかな甘酸っぱさで、暑い季節にぴったりのフレッシュなドリンクになります。
また、梅シロップは料理にも活用できます。
例えば、甘露煮の隠し味にしたり、煮豚を作るときに豚を漬け込んだりすると、梅シロップの甘みで風味が増しますよ。
手作り梅シロップについてのよくある質問
手作り梅シロップについてよくある質問を風間さんに答えていただきました。
青梅と完熟梅、どちらを使えばいい?
青梅と完熟梅は、どちらも梅シロップ作りに使えます。
それぞれに違った魅力があるため、好みにあわせて選んでみてください。
青梅は、フレッシュで爽やかな香りとすっきりとした酸味を楽しめます。
実が固いため漬けている間も崩れにくく、クリアな味わいに仕上がります。
一方、完熟梅は、桃のような甘い香りとコクのあるまろやかな風味が魅力です。
青梅に比べて実がやわらかいため、漬け始めるとすぐにエキスが出てきます。
ただし、実が崩れやすいため、砂糖と重ねて保存瓶に入れるときは、強く押し付けないようにしましょう。
梅シロップに使う砂糖の種類は何がいい?
梅シロップに使う砂糖には、「氷砂糖」「黒糖」「きび砂糖」などがあります。
一般的に使われるのは氷砂糖です。
溶けるのに時間がかかる分、梅のエキスがしっかり抽出され、透明感のあるやさしい甘さに仕上がります。
雑味が少なく発酵もしにくいため、初心者にもぴったりです。
黒糖やきび砂糖を使うと、自然な風味が加わりコクのある深い味わいに仕上がります。
ただし、黒糖やきび砂糖はミネラルが多く含まれているため、氷砂糖に比べて発酵が進みやすいといった特徴があります。
保存瓶を念入りに消毒したり、こまめに瓶を転がしたりするなど、扱いには注意が必要です。
発酵して泡が出てきたらどうすればいい?
発酵して泡が発生し、異臭もある場合は注意しましょう。
軽度であれば、梅を取り出してシロップだけを弱火で3~4分、アクを取りながら加熱し、冷ましてから再び保存瓶に戻します。
梅の実が傷んでいる場合は戻さず、シロップのみを保存してください。
なお、発酵が進むとアルコールが生成されます。酒類の製造免許を受けずにアルコール度数1%以上の飲料を製造することは法律で禁止されているため、ご注意ください。
また、カビが生えてしまった場合は、カビを丁寧に取り除いた上で、焼酎(ホワイトリカーなど)を少量加える方法もあります。
ただし、カビが広範囲にわたる場合は、安全のため廃棄するのが無難です。
梅シロップを作るのにおすすめの時期は?
梅シロップは、梅の旬である5月下旬~7月がベストタイミングです。
スーパーや直売所で新鮮な青梅が出回るため、比較的手頃な価格で手に入ります。
青梅を使う場合は、固くて傷のないものを選びましょう。
完熟梅は、やわらかく香りの良いものがおすすめです。
梅シロップ作りで夏を楽しもう

梅シロップは、材料も手順もシンプルで、初めてでも気軽に挑戦できる手作りドリンクです。
梅や砂糖の種類によって味わいが変わるのも、自家製ならではの魅力。
正しい下準備や保存方法を知っておけば、失敗の心配も減り、おいしく仕上がりますよ。
トライアルでは、梅シロップに必要な材料や保存瓶などがお手頃価格で手に入ります。
今年の夏は、手作りの梅シロップで、爽やかなおうち時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

おいしい旬の食材がいつでも安いのはなぜ?トライアルの生鮮食品の秘密