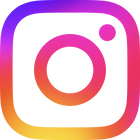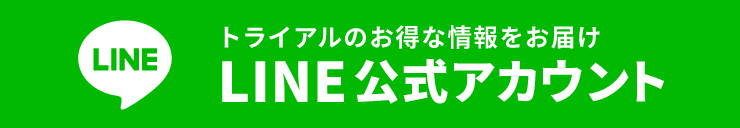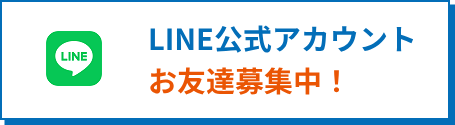【せいろの基本の使い方】選び方やお手入れ方法をわかりやすく解説
最近、SNSやテレビでも注目が集まっている「せいろ」。
試してみたいという気持ちはあるものの、「どうやって使えばいいの?」「種類がたくさんあって選べない…」「お手入れが難しそう」と、なかなか手を出せない人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、料理家の風間章子さんに、せいろの選び方や使い方、お手入れのポイントをわかりやすく教えてもらいました。
これからせいろを使ってみたいという人も、きっと気軽に使えるようになりますよ。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
教えてくれたのはこの人!

風間章子(かざま あきこ)
料理家/調理師
イタリアンレストランで6年間修業した後、カフェを立ち上げ、雑誌やウェブなど、さまざまなメディアにて料理監修で活躍。これまで、4店舗のカフェの料理メニューの立ち上げを行う。料理の技術向上はもちろん、料理の楽しさを伝えることを目的とし、料理の撮影や料理教室を開催するキッチンスタジオ「人形町キッチン」を運営。わかりやすい説明と気さくな人柄で、好評を得ている。
X(旧Twitter):@ACCO_kzm
天然素材で作られた蒸し器「せいろ」が人気の理由とは?

最近、人気が高まっている「せいろ」。
竹や杉などの天然素材で作られた蒸し器で、ナチュラルな見た目と使い勝手の良さが魅力です。
お湯を沸かした鍋の上にせいろを重ね、下からの蒸気で食材を加熱します。
せいろのここがすごい!3つの魅力
ここでは、せいろの魅力について見ていきましょう。
木の香りで癒される
せいろで蒸した料理には、ほんのり木の香りが移るのが特徴。
ふたを開けた瞬間にふわっと立ちのぼる香りに、癒されること間違いなしです。
ヘルシーでおいしい
蒸気で加熱するから、油を使わずに調理できてとってもヘルシー。
しかも、茹でるよりも水っぽくならず、食材のうま味や栄養をしっかり引き出してくれます。
重ねて使えて時短できる
せいろは、上下に何段も重ねて同時に調理ができるのも大きなメリット。
忙しいときでも手早く準備が進められます。
せいろの種類
せいろには大きく分けて「中華せいろ」と「和せいろ」の2種類がありますが、家庭で使うなら中華せいろが一般的です。
中華せいろを使ったレシピも多い上、扱いやすいため、初心者にもおすすめ。
この記事では「中華せいろ」をベースに、使い方などをご紹介していきます。
せいろの選び方

ひと口にせいろといっても、素材や大きさ、段数など、さまざまな種類があります。
ここでは、せいろを選ぶ際にチェックしておきたいポイントをご紹介します。
素材:初心者には杉がおすすめ
せいろの素材には、主に「杉」「竹」「ヒノキ」の3種類があります。
それぞれに特徴があるので、好みや使い方に合わせて選んでみてください。
せいろの素材ごとの特徴
・杉:香りがよく、価格も手ごろ。初めての人にも人気の素材
・竹:杉と比べると香りは控えめだが、杉よりも耐久性はやや勝る。リーズナブルな価格で手に入る
・ヒノキ:香り・耐久性ともに優れているが、その分お値段は少し高め
初めてのせいろには「杉」または「竹」製がおすすめです。
特に、杉のせいろはほんのり良い香りがして、料理の仕上がりにも気分が上がりますよ。
サイズ:家族構成に合わせて選ぼう
せいろは、使う人数によって、ぴったりなサイズも変わってきます。
せいろの適正サイズ
・1人暮らしや2人暮らし:直径18~21cm程
・3〜4人家族:直径24~27cm程
また、せいろは鍋にのせて使うため、お手持ちの鍋とのサイズが合うか忘れずチェックしましょう。
段数:最初は1段からスタート
せいろは重ねて使えるのが魅力のひとつ。
とはいえ、蒸気が均等に行き渡る2~3段くらいまでがおすすめです。
まずは1段から試してみて、使いこなせそうであれば、同じサイズのせいろを買い足すのもおすすめ。
重ねることで、1回の調理で一品も二品も作れて便利です。
せいろの基本的な使い方

せいろを上手に使いこなすには、いくつかのコツがあります。
使い方を間違えると、蒸気がうまく回らずに火が通らなかったり、せいろが焦げてしまったりすることも。
基本のポイントを押さえて、せいろを正しく使いましょう。
1. 使用前に水でしっかりと濡らす
せいろ本体とふたは、調理前にしっかりと水で濡らしておくのが基本です。
濡らしておくことで、底面が焦げにくくなり、せいろを長持ちさせることができます。
2. せいろに食材を並べる

濡らしたせいろにクッキングシートや葉野菜を敷き、その上に食材を並べます。
肉や魚、シュウマイなど脂や水分が出る食材を直接せいろにのせると、木に匂いや油分が染み込んでしまうため注意しましょう。
3. 鍋の湯が沸騰したらせいろをのせる

鍋に多めの水を入れ、沸騰させます。
しっかりとお湯が沸いたら、せいろをのせましょう。
沸騰前にせいろをのせてしまうと、食材の火の通りにムラが出る原因になるので、注意してください。
お湯は多めに沸かしておくのがおすすめ。
途中で蒸発してしまわないよう、様子を見ながら差し湯をすると安心です。
せいろ専用の鍋も販売されていますが、家庭にある鍋やフライパンでも代用可能です。
鍋とせいろのサイズが合わないときは、「蒸し板」を使うのもおすすめ。
せいろを安定させ、焦げつきも防いでくれる優れものです。
鍋は持ち手がふちよりも低いものや、注ぎ口がついていないものを選びましょう。
蒸気が逃げない鍋やフライパンを使用するようにしてください。
NGな鍋の例
せいろは洗っても大丈夫?長持ちさせるお手入れ方法

せいろを長く使うためには、使い終えたあとのお手入れも重要です。
ここでは、せいろを傷めずに清潔に保つための基本のお手入れ方法をご紹介します。
洗剤を使わず、ぬるま湯でやさしく洗う
せいろを洗うときは、基本的に洗剤は使わずに、ぬるま湯で軽く擦り洗いするだけで◎。
洗剤を使うと、せいろに洗剤の成分が染み込んでしまう可能性があるため、避けたほうが無難です。
汚れが気にならないときは、濡れ布巾で軽く拭くだけでも十分。
どうしても油汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めて使っても大丈夫ですが、その後はしっかり洗い流してくださいね。
風通しの良い場所で陰干しする
洗い終わったら、水をしっかりと切って、風通しの良い場所で陰干しします。
早く乾かそうとして直射日光に当てると、ひび割れの原因となるため、注意しましょう。
また、乾燥が不十分だとカビが繁殖してしまうので、しっかりと乾燥させるのがポイントです。
通気性の良いところで保管する
乾かしたあとは、湿気がこもらない風通しの良い場所で保管するのがマスト。
ポリ袋に入れて密閉してしまうとカビの原因になることも。
そのまま壁などに吊るしたり、棚に置いたりしても問題ありませんが、ほこりが気になる場合は新聞紙や布に包んで保管するのがおすすめです。
せいろの寿命は使用頻度にもよりますが、杉や竹製ものであれば1~2年が目安。
でも、正しくお手入れすれば、もっと長く使うこともできます。
我が家では、20年近く同じせいろを大切に使っています。
少しずつ風合いが増していくのも、せいろならではの楽しみです。
せいろの基本を知って、蒸し料理を楽しもう

せいろは、一度使い方を覚えてしまえば、簡単においしい蒸し料理を作ることができます。
見た目も華やかなので、そのまま食卓に出しても様になるだけでなく、お皿いらずで洗い物が減るという点も魅力的。
なにより、蒸すだけで食材そのものの味を引き出してくれるので、調味料に頼らなくても驚くほどおいしく仕上がります。
ぜひ、トライアルで販売している旬の野菜や魚など、新鮮な食材を使って、せいろ料理にチャレンジしてみてくださいね。

野菜・果物など毎日食べたいトライアルの青果、鮮度と味へのこだわり